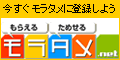気になる本とモノ
2007
今日発売のONE PIECE「ゴースト島の冒険」
ジャンプでもまだ続いている幽霊島
「ゴースト島の冒険」がようやく始まります。
でも、その前にとっても大切なのに、
思わせぶりな結末の戦いがあって。
主人公、ルフィーの兄、エースが闘う
「バナロ島の決闘」がすごすぎて。
久しぶりの登場だったのに、
エースがいなくなって残念です。
広がりすぎてる伏線をちょっとまとめたら、
再び、ルフィーたちの活躍ですね。
◆「ONE PIECE 巻46 ゴースト島の冒険」のあらすじ
黒ひげ海賊団の船長、
マーシャル・ディー・リーチと、
メラメラの実を食べた能力者、
ルフィーの兄のエースが対決する「バナロ島の決闘」。
一方、ルフィーたちは、生きたガイコツ、
ブルックと出会い、ブルックが影を奪われたことをしる。
しかし、その影を奪った謎の島、
ゴースト島「スリラーバーク」に捕らわれた一行。
伝説の名医、ドクトル・ホグバックや
ゴーストやゾンビなど不思議な
実は、この島こそ、七武海の一人、モリアの海賊船だった…
ということで、まだまだ続きそうですね、ONE PIECE。
◆「ONE PIECE 巻46 ゴースト島の冒険」の気になる言葉
24 “力”に屈したら男に生まれた意味がねエだろう 惜しいなあ、エース
56 今日はなんて素敵な火でしょう!! 人に逢えた!!! これはブルック。いい味出しています。
185 パンダマンらしき後ろ姿が…
↑読んでいただいてありがとうございました。人気blogランキングに参加しています。
2007
レネット 金色の林檎
評価 ☆☆☆ 名木田恵子 金の星社
チェルノブイリ原発事故を伏線に、
離れ離れになった家族の物語
「レネット」というのは、
原発事故の被災者の少年セリョージャが
故郷の村の形見として、
大切にしていた林檎の種の種類でした。
子供の死に直面する両親と、
被爆少年が交錯する
ちょっと物悲しい思い出の話。
2007年の読書感想文の
中学生課題図書ですが、
チェルノブイリ事故はいまや
近い過去の歴史なんだなあ、と。
◆「レネット 金色の林檎」のあらすじ
東京で母と二人暮しをしていた徳光海歌は
九年ぶりに北海道・余市に戻り、父と再会します。
その時、九年前にあずかった少年、セリョージャの話が…
十二歳で事故死した兄、海飛の穴を埋めるように、
訪れたセリョージャは被爆で弱った体の療養のため、
一月だけ余市で静養することになっていたのです。
しかし、海歌はなぜセリョージャと打ち解けられず、
ほのかな思いを抱きつつも、
ただ彼が大事にしていた林檎の種が落ちていた時に、
そっとバッグに戻してあげる程度でした。
しかし、彼の帰国直後に
海歌の家族はバラバラになっていました。
九年ぶりの帰省で、
セリョージャが現在も無事生きていることを知り、
セリョージャとの出会いが実は初恋だったことに気づきます。
さらに、海歌が気づかないうちに、
母は余市デ兄の墓参りをしていたことも知りました
家族が再び、暮らす可能性を感じながらも…
↑読んでいただいてありがとうございました。人気blogランキングに参加しています。
◆「レネット 金色の林檎」の気になる言葉
12 この九年の間、思い出に鍵をかけ、それでも思い出さずにはいられなかったあの夏のこと
51 七月でも北海道は夜の底がひんやりと白い
77 いい子(ほめるとき)…マラジェーシ
151 初恋……。セリョージャこそ、わたしの初恋。わかっていたのに、わたしは目をそむけつづけてきたのだ。
2007
世界一おいしい火山の本
評価 ☆☆☆☆ 林信太郎 小峰書店
「チョコやココアで噴火実験」というタイトルどおり、
チョコやココア、牛乳を使った実験で
火山の活動が分かる、という展開。
仕組みとしては、マグマが動く本物の火山と、
チョコが動くお菓子実験でもおなじものだとか。
夏休みの感想文を書くだけでなく、
親子で実験もできてしまうお得な本ですね。
「世界一おいしい火山の本」というタイトルは、
ウソではない、レベルの高さですね。
◆「世界一おいしい火山の本」のあらすじ
火山の基本的な説明の後、
さまざまな噴火を実験していきます。
まずは、噴火のすごさをガメラで紹介。、
渋谷の街を壊したガメラと比べてみると、
鹿児島の桜島の大火砕流の一〇〇万分の一、
という説明からして、子どもでも分かりますね。
そして、火山の爆発はコーラ、
流れる溶岩はソースで、盛り上がる溶岩はマヨネーズ。
さらに、盛り上がってくる溶岩ドームは
ココアの下から溶かしたチョコレートで盛り上げて、
実験後はトリュフチョコになる、というおいしいおまけつき。
さらに、火山の跡の穴、カルデラは
コンデンスミルクの上にココアを撒いて、
最後にミルクをしたから抜く、とできるそう。
こういう実験を楽しめる子ども達がうらやましいですね。
◆「世界一おいしい火山の本」の気になる言葉
0 宝石になったカンラン石。カンラン石は、火山から噴きだすものに入っている鉱物である。宝石として加工されたものは、ペリドートと呼ばれる。
5 キッチンで料理を作っていると、噴火で起きることとそっくりのことが、目の前で起こることがある。天ぷらを揚げているときに、まちがって水を一滴油に入れてしまうと、マグマ水蒸気爆発に似た小爆発が起こる。
18 日本列島に火山が多いのも、もとをたどると、プレートが運動することに原因がある
24 ガメラはすさまじく渋谷を破壊したが、その破壊の範囲は、小規模噴火のなかでもかなり小さめのものと同じくらいでしかない。-破壊された面積を計算すると、雲仙普賢岳の火砕流のおよそ三〇〇分の一、入戸火砕流の一〇〇万分の一以下でしかない。
29 飛ぶところを見ていさえすれば、火山弾はかんたんによけることができる
45 シリカという成分が、じつはマグマのねばりけを決めているといっていい。シリカが多ければ多いほど、ねばりけが強くなる。
65 火砕流には「高速」「高温」「高破壊力」という三つの特徴がある。
67 火砕流-上のほうの部分である「火災サージ」-その温度は三五〇℃。天ぷらやトンカツを揚げるときの油の温度が一八〇℃。クッキーやローストビーフを焼くときの温度が一九〇℃くらいである
101 富士山が噴火した場合、その火山灰は東京にまで降る可能性がある。どのくらいの被害が出るか、実際に計算した人がいる。推定被害総額が二兆五千億円。
103 火山のまわりはとても住みやすい。-第一に、火山のまわりには平らな土地が多い。第二に、火山のまわりには水が豊富である。第三に、火山のまわりには温泉が多い。第四に、火山があると風景が良い。
2007
評価 ☆☆☆ 川端裕人 角川書店
命の大切さが伝わる度 ☆☆☆
2007年の読書感想文課題図書の
「てのひらの中の宇宙」。
ガンが再発した母親を持つ家庭を描いた小説ですが、
ちょっと子ども向けにしては
内容が難しいのでは、というところがありまして、
小説の世界に入り込むのが、
ちょっと難しい気がします。
ただ、テーマは壮大な宇宙と命の話なので、
読書感想文の骨格はつくりやすいはずです。
◆「てのひらの中の宇宙」のあらすじ
妻、京子がガンの再発で入院している中、
息子ミライと娘アスカと3人暮らしを続けている崇。
母親の助けも受けているが、子ども達は
自然に対する興味がいっぱいで楽しい暮らしを続けている。
生物に興味を持ち始めたミライと話しつつ、
タカシは巨大カメを主人公にした子ども向けの話を書き始めていた。
宇宙の生成とかかわる話だったが、
一方でミライは不思議なおにいちゃんと出会う、という。
それは虫に夢中になっていた少年時代の崇自身だった。
◆「てのひらの中の宇宙」の気になることば
33 人間は死んだら空気に溶け込むけど、それを草や木が食べる。草や木の中には人間だって入っている。…ママが死んだときの話として。
172 ぼくたちは、何にも護られることなく、直接、宇宙の巨大さの前に晒されている。
↑読んでいただいてありがとうございました。人気blogランキングに参加しています。
2007
評価 ☆☆☆ 三浦 博史 青春出版社
参議院選挙でお役立ち度 ☆☆☆
“選挙参謀”という仕事をしている著者が
選挙の裏側を少しだけ紹介しています。
小選挙区制になって変わったこと、
選挙にかかるお金など、選挙を手伝う人、
選挙に興味がある人、
そして選挙に出る人にはとっても勉強になりますね。
でも、一番大切なことは熱い思いの
“熱伝導”なんですね。
そして、一番、熱を伝えられた政治家は…
◆「舞台ウラの選挙」のあらすじ
「選挙にはいくらかかるのか」から始まって
「票はこうして集まる」
「そのお金は“誰が”出す?」
「PR上手が心をつかむ」
と技術的な話が続きます。
裏話的にはこっちのほうが面白いんですが、
やっぱり大切なのは心。
「人を動かす決め手とは」
「こんな人が最後に勝つ」
と後半に心を打つ姿勢が出てきます。
そして、一番心を打った人として、
田中角栄元総理が出てきます。
最強の後援会、超山会の原点は
有権者の思いの強さなんですね。
◆「舞台ウラの選挙」の気になる言葉
23 供託金といわれるもので、最も金額が高いのが国政の比例区選挙の六〇〇万円、最も安いのが政令指定都市以外の市議会議員選挙と東京二三区の区会議会議員の三〇万円
31 告示日までの半年間は、投票依頼の選挙運動は禁止されている。-後援会入会勧誘活動といい、告示日前日まで合法的に行えるものだ
35 市議会議員の選挙費用の全国平均は、公費負担を除いた持ち出しで約二〇〇万円という数字もある
53 中選挙区では自民・保守系の候補が乱立することで、選挙費用の相場がおのずと上がっていく形になっていたのである
59 選挙でいうサードレールとは、決して選挙運動で触れてはいけないイシューを指すようになった。サードレールの主なイシューはせいぜい五~六くらいしかないのだが、その第一が年金なのだ。-年金を選挙の争点にすると自らのクビを絞めてしまうから、選挙戦のイシューにはしないのである
73 知事選でも小口の個人献金の収入を増やしていくという傾向が、だんだん強くなってきている。
76 (落選後)秤量攻めに耐えられる候補者は、奥さんが理解者だったり、奥さんの実家がそこそこ資産を持っていたりする人に多い。
83 政党助成金は選挙ブローカーを断る絶好の口実にもなった。
107 候補者と有権者との間に意識のギャップがないかどうか検索するのである。それによって、ギャップのない、あるいは少ないイシューは外し、ギャップの大きなものだけを浮かび上がらせて、争点にするわけだ
110 女性は違う。ブレる人が大嫌いなのだ。なぜ発言がブレたのかを理解する前に、ブレたこと自体に嫌悪感を持つ人が多い。
149 ウグイス嬢ではなく、若い男性の運動員前に出したほうがプラスになるケースもあるはずだ。-“カラスボーイ”
153 選挙のやり方では、風土よりもと都市部と軍部による違いのほうが大きい。
191 越山会会員は、それぞれ角栄にまつわる事実に基づいたエピソードを持っているから、他人からどういわれようと、「自分は終生、田中先生を支持していく」と力強く主張することができる
↑読んでいただいてありがとうございました。人気blogランキングに参加しています。